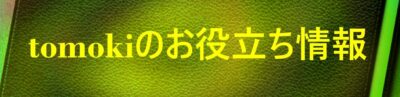【天の数歌】古神道の音の力で心と魂を整える。瞑想に活かす数え歌の力
私たちが何気なく口にする「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という数え方。
それが、実は深い意味と力を秘めた日本古来の祝詞の一部であることをご存じでしょうか。
これは「天の数歌」と呼ばれ、古神道に伝わる神聖な音の並びとされています。
単なる数ではなく、言霊として魂や宇宙の秩序を整える音霊なのです。
天の数歌とは? 日本古来の神聖なカウント
「ひと、ふた、み、よ、いつ、むゆ、なな、や、ここの、たり」
このリズム感のある数え歌は、子ども時代に耳にしたことがある人も多いかもしれません。
しかしこの言葉、実は古神道の中で宇宙や自然の調和を表す音霊として大切にされてきました。
続く「もも、ち、よろず」は、「百」「千」「万」を表し、数の大きな広がりを意味しています。
この数歌は、ただの数字ではなく、
天地の生成や森羅万象の流れを表した神聖な音として、神事や瞑想、浄化儀式に使われてきたといわれています。
瞑想時に唱える「天の数歌」の効果とは?
現代においても、この天の数歌を瞑想や呼吸法に取り入れる人が増えています。
その理由は、次のような効果が期待できるためです。
1. 心の静けさと集中力を高める
言葉にリズムがあることで、呼吸が整い、雑念が消えやすくなります。
特に「ひと、ふた、み、よ…」と口に出して繰り返すことで、マントラのように心を沈める効果があります。
2. チャクラやエネルギーの調和
各音に特定の波動があるとされ、
繰り返すことで身体のエネルギーが整いやすくなるという報告もあります。
3. 浄化と整えの効果
この音の連なりは、神道における清めの力を象徴しているとも言われています。
つまり、唱えることで自然と心身の浄化が促されるという考え方です。
神道の祝詞と音の浄化力
天の数歌と並んで、神道では「祝詞」と呼ばれる祈りの言葉も大切にされてきました。
たとえば次のような祝詞があります
天津祝詞 御祓の祓詞
「掛けまくも畏き伊邪那岐大神
筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に禊ぎ祓え給ひし
時に成り坐せる祓戸大神たち諸の禍事・罪・穢れを祓え給へ清め給へと申すことの由を聞食せと畏み畏みも白す」
これはどういう意味という疑問について詳しく解説。
これは「伊邪那岐命」が
禍事や穢れを洗い流した神話の場面を元にした祓詞です。
神道では、「音と言葉」には実際に浄化と変容の力があるとされ、
こうした祝詞を唱えることで目に見えない邪気や曇りを祓うと考えられています。
音を通して自然とつながる
「天の数歌」や祝詞のような日本の伝統的な音の文化には、現代の私たちが忘れかけている自然との一体感があります。
特に「たり」や「もも」「ち」「よろず」といった終わり方は、

数を閉じるのではなく、循環の中にある生命の広がりを感じさせてくれます。
これを瞑想の中で唱えることで、個としての自分と、大きな自然や宇宙とのつながりを感じる時間を持つことができるのです。
天の数歌を活かすおすすめの瞑想法
以下は、初心者にもおすすめの「天の数歌瞑想」の一例です
-
静かな場所に座り、姿勢を整える
-
ゆっくりと深呼吸を3回
-
「ひと、ふた、み、よ、いつ、むゆ、なな、や、ここの、たり、もも、ち、よろず」と静かに唱える(3回繰り返し)
-
唱え終えたら、余韻の中で1分間ほど静かに座る
-
最後に深呼吸して瞑想を終える
このシンプルな方法だけでも、頭がすっきりしたり、気持ちが整ったりすることがあります。
また、言葉の意味を深く考えず、音として味わうことで、より言霊としての力を感じやすくなるでしょう。
【まとめ】古の音に心を預ける
「天の数歌」は、単なる古語の数え歌ではありません。
そこには、宇宙のリズムと生命の調和を音に託した日本人の知恵と感性が込められています。

現代の私たちは、情報や刺激の多さに心が疲れがちです。
そんなときこそ、このような「シンプルで静かな言葉」と向き合うことで、
本来の自分と、自然の一部である感覚を取り戻すことができるかもしれません。

あなたも今日、静かな時間に「ひと、ふた、み…」と口ずさんでみませんか?
その音の先に、懐かしくも新しい自分の中心が見えてくるかもしれません。